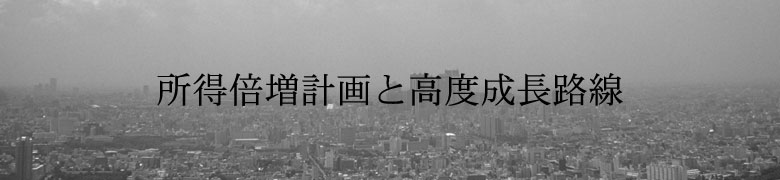安保闘争
昭和35年5月19日、衆議院本会議で改定日米安全保障条約の批准案が自民党の主流派だけで強行裁決されました。これ以後安保反対闘争は、文化人、学生、労働組合員などが中心となり、国会を連日取り巻くという異常な事態に発展していきました。総評を中心とした労働組合員は6月4日と15日の両日ストに突入し、6月10日にはアイゼンハワー大統領の訪日の打ち合わせのために来日したハガチー新聞係秘書が弁天橋の手前で約8000人のデモ隊に包囲され、アメリカ軍ヘリコプターによって脱出するという事態も起きました。この脱出劇については自衛隊がショックを受けたようです。アイク来日の際、緊急事態が発生した場合にアイクがアメリカ軍に助けられるのは許されるにしても、日本の天皇陛下がアメリカ軍に助けられるのは国辱ということになります。天皇、大統領に羽田より皇居の間において万一のことのある場合、アメリカ側より天皇が救出されたとあっては自衛隊の面目にもかかわるので、陸幕はヘリコプターを準備しているということです。もちろん政府の方針に従って動くのが前提ですが、注目すべきことは真偽はともかく、ハガチー氏の来日に対して暗殺を含む阻止行動をソ連、中国共産党、日本共産党の三者が検討したとする香港情報が外交文書に登場していることです。冷戦の厳しさがこのような情報にも表れています。
昭和35年6月15日、警官隊と全学連を中心とするデモ隊が国会構内で衝突し、東大生樺美智子が死亡。翌16日岸内閣は閣議でアイゼンハワー大統領の訪日の延期を決定し、さながら内乱の様相を呈していました。この死亡事故を機に新聞世論が一変し、17日には在京7社の新聞が共同宣言、暴力を排し議会主義を守れを発表。運動は沈静化の方向に向かいはじめました。18日には空前の38万人が国会を包囲し、19日、条約案は自然成立。20日、岸内閣は退陣を表明し、安保闘争は終結しました。昭和26年9月8日に締結された日米安全保障条約は、アメリカ軍の駐留を認めながら、アメリカは日本への防衛に責任を負わない、あるいはアメリカ軍の行動が事前協議の対象になっていないなどの片務的条約となっていました。このために昭和32年2月25日に発足した岸内閣は33年に藤山愛一郎外務大臣をアメリカに派遣、ダレス国務長官と改定交渉に入りました。そして、昭和35年1月19日に岸首相がアメリカで条約に調印するに至りました。社会党、総評、中立労連、護憲連合、全国基地連、原水協、日中国交回復国民会議、日中友好協会、平和委員会、全日農、人権を守る婦人協議会、青年学生共闘会議、東京共闘などの13団体を幹事団体として約134団体で昭和34年3月28日に組織された安保条約改定阻止国民会議を中心とする改定反対運動は、昭和34年8月の原水禁大会以後急速に盛り上がりを見せました。
日米安全保障条約の正式名称は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約。サンフランシスコ平和条約と同時に結ばれた旧安保条約にかわるものとして昭和35年1月19日に調印され、翌36年6月23日に発効しました。第5条は、日本国の施政下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自由の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動すると定め、第6条は、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許されるとしており、これが同条約の柱です。第6条について、アメリカ軍の軍事行動に日本が巻き込まれる恐れがないかが国内の論争点とされ、ベトナム戦争や沖縄返還との関係で事前協議制や極東の範囲について与野党との対立が続いてきのましたが、不毛の論争でした。第10条の10年間の固定期限は昭和45年で切れ、現在は自動継続期間です。一方の廃棄通告があれば、1年間の予告期間後に廃棄されますが、日米双方とも同条約の堅持を基本方針としています。昭和44年の佐藤ニクソンによる日米共同声明で、日本側は韓国・台湾地域の安全は日本のそれと一体と見る認識を明らかにし、この地域に紛争が起きて、アメリカから在日基地を使った米軍の出撃について事前協議があれば、許諾の回答をする旨を示唆しました。この台湾・韓国条項は、事前協議制のもつ歯止めの意味を否定した、安保条約の質的強化といわれました。しかし、昭和48年の日中国交正常化や米中接近で台湾条項の実質的重みが減り、一方の朝鮮半島にも南北対話の機運が高まるなど、冷戦外交の基本構造として生まれた日米安保条約も、その基礎は崩れ始めました。
昭和34年9月12日に始まった社会党の第16回大会は大荒れでした。ことの発端は、西尾末広が日米安保条約の段階的解消を主張していことと、日華協力委員会のメンバーであることを理由として統制処分に付されたことでした。大会開始直後の9月18日に西尾派の再建同志会代表世話人の伊東卯四郎が単独で離党し、ついで10月25日西尾派の32人が離島し、社会クラブを結成しました。11月25日には河上丈太郎派の12人が離党し、社民クラブを結成しました。30日には再建同志会と合流し、民主社会主義新党準備会を発足させて、昭和35年1月24日、西尾末広を委員長、曽根益を書記長とする民主社会党を結成しました。同党は社会民主主義を政治理念として、全日本労働組合会議の支持をバックにゆるやかな政治社会改革の実現をめざしました。全日本労働総同盟発足後は、同盟の支持を全面的に仰ぎ、イエスかノーかという過激に走りがちな社会党、共産党の政治姿勢を批判し続け、健全な野党、政権のとれる野党をめざしています。しかし、その志に反して勢力は伸びず、その後の選挙でも結党時の55人を回復しきれないまま、平成6年12月9日に解党、新進党の結成に丸ごと参加し、その役割を終えました。
昭和35年7月、安保改定に政治生命をかけた岸信介に対する風当たりは日増しに強くなっていきました。特に昭和35年6月に入って政局はにわかに緊張の度を加え、社会党が6月1日に議員総辞職の方針を決定したあと、自民党内からも三木、松村、石橋、河野の反主流3派から岸首相の即時退陣が出されました。そして、6月4日には安保改定阻止のためのゼネスト的実力行使が行なわれ、全国54単産、400万人が参加しました。6月10日にはハガチー事件が起り、アイゼンハワーの新聞係秘書官ハガチーが羽田で全学連のデモ隊に囲まれて立往生しました。6月15日夜は全学連のデモ隊が国会に突入し、学生の一人、樺美智子が死亡するという最悪の事態となりました。アイゼンハワーの訪日は数日後に迫っていました。16日の未明に開かれた緊急臨時閣議では国家公安委員長の石原幹市郎が警備力に限界があると発言しました。連日開かれていた治安閣僚懇談会では佐藤栄作、池田勇人らが防衛庁長官赤城宗徳に自衛隊の出勤をしばしば促していました。岸自身も自衛隊出勤に踏み切るかどうか重い迷っていたようです。わずかな数でも自衛隊を使ったということで、外国には内乱と受取られる公算が大きいと消極的な意見をもらしたこともありました。しかし、岸は6月15日、赤城を呼び、自衛隊出勤を強く要請します。赤城は自衛隊が出勤する以上、一発勝負でデモを鎮圧しなければならない。そのためには機関銃などで武装しなければならず、それでは同胞相克の残酷物語となって、内乱的様相に油をそそぐとの理由に反対しました。翌16日に岸は臨時閣議を開き、アイゼンハワー大統領の訪日延期を決定しました。岸はこの時点で安保批准後辞任の決意をはっきり固めたと思われます。川島副総裁などはかねてから解散論を唱えており、岸も一時はそれにはげまされたこともあったようです。6月21日岸は川島幹事長に辞任を示唆し、続いて23日朝、日米安保条約の批准書を交換の直後、正式に辞任を表明しました。岸の日本再建の夢はここに終わり、憲法改正、小選挙区制、警職法改正などのその夢は次々と打ち破られてきました。わずかに日米不平等条約の是正を、岸の当初の意気込みからすれば極めて不本意な形で、それも辛うじて果たしたということです。
池田勇人は大蔵事務次官を勤めた後、昭和24年1月23日の総選挙で政治家としての一歩を踏み出しました。そしてその時の第3次吉田内閣の大蔵大臣に抜擢されました。第4次吉田内閣では通産大臣、石橋内閣でも大蔵大臣、続く岸内閣でも大蔵、通産大臣を経験し、当選以来政治の中枢を歩んできました。そして経済成長の見通しは、過去の実績から見て、36年度以降3ケ年に年平均9%は可能であり、国民所得を一人あたり12万円から昭和38年度には約15万円に伸ばします。これを達成するために適切な施策を行なって行けば、10年後には国民所得は現在の倍になるという発表をしました。経済の動きからすれば、その通りなのですが、それを国民所得倍増といい、庶民の感覚で表現したことに池田の真骨頂がありました。その1年半程前、池田は昭和34年2月、郷里広島で記者会見を行ない、このときに所得倍増論を言い経済成長は敗戦直後からの日本の基本政策であったかのように思われていますが、決してそうではありませんでした。この当時は経済の引き締めが基本であり、投資を中心とする池田の理論は異端でした。池田は数字に強く、しかも強いばかりでなく誰でもが理解できるような物に置き換えて表現するという庶民感覚の持ち主でもありました。吉田が体を張って進めてきた軽武装と経済中心主義は池田によって完全に日本国民の中に定着しのした。その意味では池田は日本国民に今後の道筋を具体的に表したといえます。池田内閣は公共投資と減税と社会保障を国内経済の中心とし、農業基本法、中小企業基本法の制定など経済成長にふさわしい国内体制づくりを進めていきました。
昭和35年6月23日、岸首相が辞意を表明してからの自民党内は後継総裁を誰にするかという権力継承問題を中心に、官僚派と党人派の対決によるみにくい抗争の修羅場となりました。そして、7月14日に行なわれた総裁公選によって、池田勇人が石井光次郎と藤山愛一郎という対抗馬を打ち破って総裁に選ばれ、続いて7月18日に開かれた国会で総理大臣に指名されました。第1次池田内閣が発足したのはその翌日の7月19日のことですが、この時日本で最初の女性閣僚として中山マサが厚生大臣に選ばれました。60年安保闘争であれだけ激しい体制運動を繰り広げたにも関わらず、自民党の保守優位体制は全く崩れませんでした。池田内閣成立の直後、社会党をはじめとする革新勢力は、岸亜流政権反対を唱え、日比谷公園に集まったデモ隊も池田政権反対を声を限りに叫びましたが、一般の国民を動かすことはできませんでした。しかし、池田勇人は7月19日にいちはやく国民に対して次のような談話を発表し、低姿勢の政治を強調しました。
私はまず内外にわたり政治の信用度を回復するために、与党ならびに在野の友党と協力し、議会政治の確立に努力を傾ける。私はつとめて政治の姿勢を正し、政策の着実なる具現を図り、もって国民の優れた資質の正しい展開に資したいと存じます。
内閣の発足した昭和35年は、安保騒動の余韻の冷めやらぬ頃で、池田内閣の使命がこの騒動で荒れ果てた人心の一新にあることは誰の目にも明らかでした。人々の力を建設的な方向に向けなければというのが池田の基本的な考え方でした。
copyrght(c).SINCE.all rights reserved